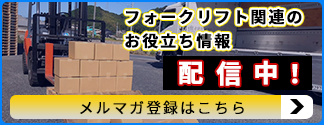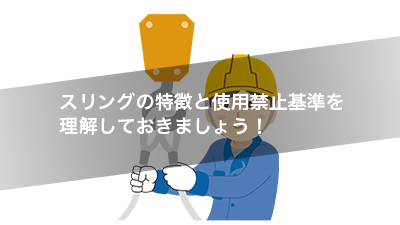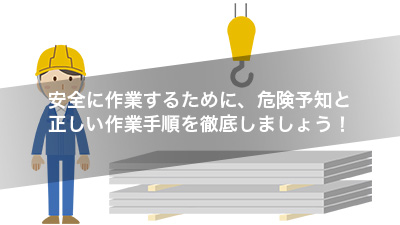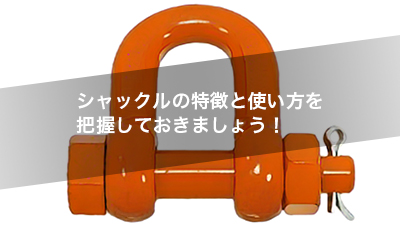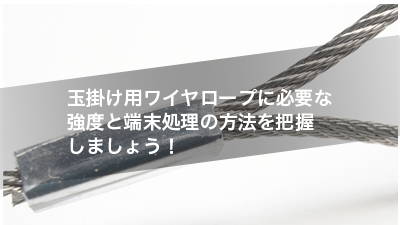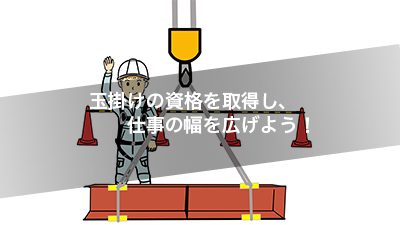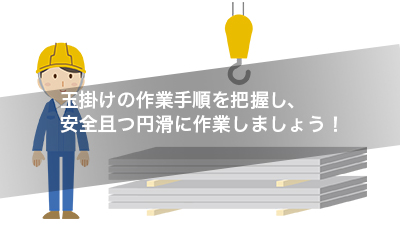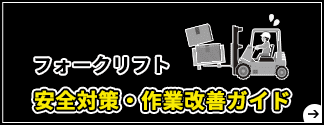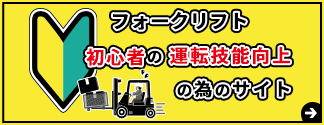<玉掛け作業の安全啓発>吊り荷の下には入らない!
玉掛け作業における吊り荷の下への立ち入りは、重大な事故に繋がる非常に危険な行為です。吊り荷の落下や、荷が振れたり倒れたりすることに巻き込まれるリスクがあるため、絶対に避けるべき行動です。
一見、問題なく吊られているように見えても、玉掛け方法のわずかな不備や用具の劣化、あるいは突発的なクレーン操作によって、数トンにも及ぶ吊り荷は一瞬にして凶器と化します。ひとたび落下事故が発生すれば、作業員の生命を奪う死亡災害に直結します。
今回のコラムでは、なぜ「吊り荷の下に入ってはいけないのか」という基本原則を掘り下げます。実際に発生した痛ましい落下・下敷き事故の事例と、作業員の安全を守るための法的根拠(クレーン等安全規則第29条)を紹介しますので、「吊り荷の下には絶対に入らない!」を現場で徹底するための安全意識を再確認しましょう。
1秒で伸縮でき、携行できる玉掛専用の手カギ棒はこちら!
吊り荷の下に入る危険性
玉掛け作業において「吊り荷の下に入らない」ことが絶対的なルールとされているのは、命に関わる重大な事故に直結する非常に高い危険性があるためです。
主な理由としては、吊り荷の「落下」による直撃・下敷きです。
吊り荷が何らかの原因で落下し、作業者が直撃を受けたり、下敷きになったりする事故です。
その吊り荷が落下する原因を以下に挙げていきます。
【玉掛け方法の不備】
- ワイヤーロープの掛け方(角度、重心など)が不適切で、荷崩れや滑りが発生する。
- フックの外れ止めが機能していない、またはハッカーやクランプの使用方法が不適切で、吊り荷が外れる。
【玉掛け用具の破損・切断】
- ワイヤーロープ、スリング、シャックルなどの点検不足や過荷重により、使用中に破断・切断する。
【クレーン操作上の問題】
- 急な操作や衝撃により、吊り具が破損したり、荷がバランスを崩して外れたりする。
【玉外し時の二次災害】
- 着地後、玉外しのために吊り荷の下に入った際、荷が倒れたり転がったりして下敷きになる。
吊り荷が落下した事故事例
玉掛け作業で吊り荷が落下し、作業者が下敷きになった重大な事故事例は多数報告されており、その多くは「吊り荷の下への立ち入り禁止」という基本原則が守られなかったこと、または不適切な玉掛けが原因で発生しています。
特に死亡災害につながりやすい具体的な事例をいくつかご紹介します。
1. 不適切な玉掛け方法による荷の落下
事例:ワイヤーロープの「半掛け」と鋼管の落下
発生状況: トラックに積まれた鋼管(滑りやすい)をクレーンで荷下ろしする際、玉掛け作業員がワイヤーロープの端をフックに引っ掛ける「半掛けという不適切な方法で玉掛けを行った。
事故の経緯: クレーンで鋼管を吊り上げたところ、玉掛け方法が不適切だったため、鋼管がワイヤーロープから滑り落ち、近くにいた作業員(トラック運転手など)を直撃、または下敷きにした。
主な原因:
- 不適切な玉掛け方法(半掛け)の選択。
- クレーン運転手が不適切な玉掛けのやり直しを要求しなかった。
- 作業員が吊り荷の落下するおそれのある場所(危険区域)に退避していなかった。
2. 玉掛け用具の不備・不具合による荷の落下
事例1:フック外れ止め機構の不全による部材の落下
発生状況: プラント解体工事で、移動式クレーンを用いて解体済みの部材をトラックに積み込む作業を行っていた。
事故の経緯: 吊り上げていた部材が突然落下し、近くにいた作業員が下敷きになり死亡。
主な原因:
- 玉掛けに使用していたフックのロック(外れ止め)機構が有効に作動しない状態になっていた(点検不足)。
- ロック機構の不具合により、吊り荷がフックから外れやすい状態でありながら作業を続行した。
- 作業員が吊り荷の真下または極めて近傍に立ち入っていた。
事例2:ワイヤーロープの切断による吊り荷の落下
発生状況: 重量の大きい鋼製収納庫(約4.17トン)を天井クレーンで吊り上げ、移動させている最中に発生。
事故の経緯: 玉掛けに使用していたワイヤーロープが突然切断し、収納庫が落下。吊り荷の近くで移動の補助をしていた作業員が下敷きになり死亡。
主な原因:
- 使用したワイヤーロープが不適切な太さ(強度不足)であった(径10mmを使用)。
- 吊り角度が極端に大きくなり、ワイヤーロープに設計上の許容張力(破断荷重)を超える過大な負荷がかかった。
- ワイヤーロープの点検を怠り、損傷や劣化のあるものを使用していた可能性。
- 吊り荷が荷台から少し浮いた状態で、作業員が荷に手を添えながら移動しており、危険区域に立ち入っていた。
これらの事例から、吊り荷の下敷き事故は、主に「玉掛け方法の不備(技術的要因)」と「吊り荷の下に立ち入る行為(人的要因)」が複合的に重なることで発生することがわかります。安全な作業のためには、有資格者による適切な玉掛けに加え、「吊り荷の下には絶対に入らない」というルールを徹底することが最も重要です。
1秒で伸縮でき、携行できる玉掛専用の手カギ棒はこちら!
クレーン等安全規則第29条について
クレーン等安全規則第29条は、「つり荷の下への立ち入り禁止」を事業者に義務付けている、玉掛け作業の安全を確保するための極めて重要な条文です。
この条文は、特に危険性の高い玉掛け方法で荷が吊り上げられている場合について、事業者が労働者をつり荷の下に立ち入らせてはならないことを定めています。
クレーン等安全規則 第29条の解説
1. 規定の目的と原則
この条文の目的は、荷の落下や外れによる重大な人身事故を未然に防ぐことにあります。
・規定の主体: 事業者(会社や現場の責任者)に対し、立ち入り禁止の措置を講じる義務を課しています。
・原則: クレーン等に係る作業を行う場合、特定の危険な玉掛け方法が使われているときだけでなく、原則として労働者を荷の下に立ち入らせないように努めることが求められています。
2. 立ち入りを禁止しなければならない「特定の危険な玉掛け方法」
クレーン等安全規則第29条では、特に荷が不安定になりやすく、落下や外れのおそれが高い以下の玉掛け方法で荷が吊られている場合、つり荷の下(直下および荷が振れるおそれのある範囲)に労働者を立ち入らせてはならないと定めています。
| 号 | 玉掛け方法 | 危険な理由 |
|---|---|---|
| 一 | ハッカーを用いて玉掛けをした荷 | 爪を荷の端に引っ掛ける方法で、荷が傾くと外れやすく、バランスが不安定になりやすい。 |
| 二 | つりクランプを1個だけ用いて玉掛けをした荷 | クランプ1個のみでは、荷が振れたり衝撃が加わったりした際にクランプ力が弱まり、滑り落ちる危険性が高い。 |
| 三 | ワイヤロープ、つりチェーン、繊維ロープ、繊維ベルトを用いて1箇所に玉掛けをした荷 | 荷の回転や傾きが起こりやすく、荷崩れやロープの外れにつながりやすい。(ただし、穴やアイボルトにロープ等を通して玉掛けしている場合を除く) |
| 四 | マグネットやバキュームパッド(真空吸着)などを用いて玉掛けをした荷 | 停電や吸着力の低下、荷の表面状態の変化などにより、突然荷が落下する危険性が高い。 |
| 五 | 動力による降下以外の方法で荷を降ろすとき | 自由降下(ブレーキのみに頼る降下)は、衝撃や速度制御のミスにより荷が不安定になりやすい。 |
| 六 | その他、上記の玉掛け方法に準ずる危険な方法 | 例:外れ止めが付いていないフックの使用など、荷の外れる危険性が高い玉掛け用具を用いるとき。 |
3. 事業者が講じるべき措置
事業者は上記のいずれかの方法で作業を行う場合、単に口頭で注意するだけでなく、以下の措置をとることが義務付けられています。
- 禁止の表示: 立ち入り禁止の旨を見やすい箇所に表示する。
- その他の方法: 立ち入りを禁止するために必要な監視員の配置や、立ち入り禁止区域の明示などの措置を講じる。
これらの規制は不確定要素が多く、落下のリスクが高い玉掛け方法から作業者を守るための最低限の安全基準であり、「吊り荷の下には入らない」という鉄則を担保する法的根拠となっています。
まとめ
本コラムでは、「吊り荷の下には入らない!」という玉掛け作業の絶対原則について、その危険性、具体的な事故事例、そして法的な裏付け(クレーン等安全規則第29条)を通して再確認しました。
【命を守るための鉄則再確認】
- 事故は複合要因で起こる: 荷の落下は、「玉掛けミス」や「用具の不備」といった技術的要因に、「吊り荷の下への立ち入り」という人的要因が重なることで発生し、重大災害に直結します。
- 規則は命綱: 特に危険度の高い玉掛け方法(ハッカー、クランプ1個、マグネットなど)使用時は、クレーン等安全規則第29条により、事業者は労働者の立ち入りを厳しく禁止することが義務付けられています。
作業の効率や手直しの誘惑があっても、「吊り荷の下は、常に落下する危険がある場所である」という意識を絶対に持ち続けてください。
「大丈夫」は禁物です。 適切な玉掛け技術と、「絶対に近づかない」という強い意志をもって、自分の命と仲間の安全を守りましょう!
1秒で伸縮でき、携行できる玉掛専用の手カギ棒はこちら!